外付けディスプレイを選ぶとき、まず気になるのが“サイズ”。ところが「○○インチ」と言われても、実際の大きさや作業感はピンと来ないことも多いですよね。ここでは、インチ表記の見方をやさしく整理し、画面比率(アスペクト比)の違いも踏まえたうえで、用途ごとの選び方をまとめます。
インチとセンチの関係/サイズ表記の基本
モニターの「○○インチ」は画面の対角長を示します。
1インチ=2.54cm。たとえば27インチは約68.6cmの対角です(27×2.54)。
同じインチでも画面比率が違うと、縦横の実寸や表示面積は変わります。つまり「インチ数=体感の広さ」ではありません。比率と表示解像度までセットで考えるのがポイントです。
かんたんサイズ早見(代表的な画面比率別)
下の表は、よく選ばれるインチで**縦×横の目安(cm)**をまとめたものです。
※おおよその値です(ベゼルや本体外形は含みません)。
計算の前提
- 16:9(一般的な動画向け)
- 16:10(縦に少し余裕)
- 3:2(さらに縦が長め)
| 型(インチ) | 対角(cm) | 16:9 縦×横 | 16:10 縦×横 | 3:2 縦×横 |
|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 33.8 | 約16.6 × 29.5 | 約17.9 × 28.7 | 約18.8 × 28.1 |
| 14.0 | 35.6 | 約17.4 × 31.0 | 約18.8 × 30.2 | 約19.7 × 29.6 |
| 15.6 | 39.6 | 約19.4 × 34.5 | 約21.0 × 33.6 | 約22.0 × 33.0 |
| 23.8 | 60.5 | 約29.6 × 52.7 | 約32.0 × 51.3 | 約33.5 × 50.3 |
| 27.0 | 68.6 | 約33.6 × 59.8 | 約36.3 × 58.2 | 約38.0 × 57.1 |
| 32.0 | 81.3 | 約39.8 × 70.8 | 約43.1 × 68.9 | 約45.1 × 67.6 |
ワンポイント
同じインチなら、縦が長い比率ほど総面積は大きくなります。たとえば13.3インチでも16:10 や 3:2の方が縦が伸び、文書やコードの見やすさがアップ。
用途別のおすすめサイズ
仕事(文書・表計算・Web・在宅勤務)
- 24~27インチが扱いやすい定番。
2枚並べるなら24インチ×2、または27インチ+縦置きサブも快適。 - 比率は16:10や3:2だと縦情報が増え、スクロール回数を減らせます。
ゲーム
- 24~27インチが主流。視線移動が少なく、競技系でも把握しやすい。
- 高リフレッシュレート(144Hz~)や低遅延も要チェック。
- 画面との距離が近いなら24、余裕があれば27。
クリエイティブ(画像・DTP・動画編集・3D)
- 27~32インチが作業領域をしっかり確保。
- カラーマネジメント(広色域・工場校正)や高解像度(WQHD/4K)との相性がよい。
- タイムラインやパネルを出しっぱなしでも窮屈になりにくい。
映画・動画視聴
- 32インチ以上で没入感が高まる。
- 離れて見るなら大きめ、近距離なら27~32で画素密度と視聴距離のバランスを。
アスペクト比(16:9/16:10/3:2)の選び分け
- 16:9
いちばん普及。動画やゲームの互換性が高く、価格帯も豊富。 - 16:10
縦が少し増えるため、文書や表、ブラウズが快適。仕事向けの“ちょうど良さ”。 - 3:2
さらに縦長。テキスト中心・研究用途・開発に向く。対応モデルはまだ限られる。
迷ったら
動画重視=16:9、作業重視=16:10、縦情報重視=3:2が目安。
まとめ:失敗しないサイズ選定のコツ
- 作業距離と設置スペースを先に測る
机の奥行き・視聴距離・スタンドの占有を考慮。大きすぎは首・目の負担に。 - サイズだけでなく比率を見る
同インチでも16:10/3:2は縦が増えて快適さが変わる。 - 総コストは“解像度や機能”込みで
端子(USB-C給電・KVM・ハブ機能)、高さ調整、色域、リフレッシュレートも生産性に直結。 - 用途別の“定番レンジ”に乗せる
仕事=24~27、ゲーム=24~27、制作=27~32、映像鑑賞=32以上が無難。
モニターは毎日目に入る“作業環境そのもの”。サイズ・比率・機能のバランスを押さえ、自分の使い方に合った一台を選びましょう。

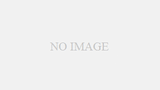
コメント