深夜に「100均でちょっと買い物したい」と思ったことはありませんか?コンビニほどの品揃えは必要なく、ちょっとした日用品や文房具、キッチン用品を手に入れたい場面は意外と多いものです。しかし、日本では24時間営業の100均はほとんど見かけません。その理由は何なのでしょうか?
本記事では、100均の24時間営業が少ない背景や、深夜営業のメリット・デメリット、そして今後の可能性について詳しく解説します。仕事帰りや夜型生活の方にとって、100均の深夜営業が便利である一方で、店舗運営側にはさまざまな課題があるのも事実。これからの100均業界において、深夜営業は増えていくのか、それとも現状のままなのか?その理由を探っていきましょう!
100均の24時間営業とは?
24時間営業のメリットとデメリット
メリット
- 仕事帰りや夜中に急な買い物ができる。
- シフト勤務や夜型生活の人にとって便利。
- 混雑を避けて買い物ができる。
- 深夜帯でも必要な生活必需品が手に入る。
- 昼間に買い物できない人にとって大きな利便性がある。
- 旅行者やイベント帰りの人にも便利。
- コンビニよりも低価格で商品が揃う。
デメリット
- 人件費や光熱費が増加。
- 深夜帯の防犯対策が必要。
- 来店客数が少なく、採算が合わない可能性。
- 商品の補充や管理が難しくなる。
- 24時間営業が可能な店舗の立地が限られる。
- 深夜の時間帯にスタッフを確保するのが困難。
- 需要が限定的で売上が伸びにくい。
深夜営業が可能な理由
- 大型商業施設内にある場合、テナントとして24時間営業がしやすい。
- 駅や繁華街に立地する店舗は需要が見込める。
- コンビニ併設型の100均は深夜営業しやすい。
- 防犯設備が充実しているエリアでは営業しやすい。
- 夜間の交通量が多いエリアでは一定の集客が見込める。
- 無人レジやキャッシュレス決済の導入で人件費削減が可能。
- 一部の100均はスーパーと併設し、夜間利用者の利便性を向上させている。
- フードデリバリー需要の増加に伴い、24時間営業の100均も役立つシーンが増えている。
- AIやセンサー技術の発展により、無人店舗の可能性も広がっている。
24時間営業の需要と実際の利用状況
- 夜勤労働者や学生の利用が多い。
- しかし、日中に比べると利用者数が少ない傾向。
- 深夜帯は特定の商品(電池・文具・食品類)の購入が目立つ。
100均の営業時間
各店舗の営業時間の違い
- ショッピングモール内の100均:モールの営業時間に準ずる。
- 独立店舗の100均:通常10:00~20:00が多い。
- コンビニ併設型:深夜営業可能な場合あり。
主要エリアの100均店舗
- 東京・大阪・名古屋などの大都市では深夜営業の店舗が点在。
- 地方都市や郊外では営業時間が短めの傾向。
深夜営業の店舗リスト
- 一部のダイソーやキャンドゥが深夜営業対応。
- 大都市圏の繁華街に限定されることが多い。
100均の営業時間
各店舗の営業時間の違い
- ショッピングモール内の100均:モールの営業時間に準ずるが、一部の大型モールでは21:00や22:00まで営業する店舗も増加。
- 独立店舗の100均:通常10:00~20:00が多いが、都市部では22:00や23:00まで営業する店舗も存在。
- コンビニ併設型:深夜営業可能な場合あり、特に繁華街の店舗では需要が高いため24時間営業を行う店舗もある。
- 一部のロードサイド型店舗では、深夜1:00や2:00まで営業している例も見られる。
- フランチャイズ展開している100均では、店舗ごとに営業時間が異なることが多い。
- 観光地にある店舗では、土日祝日の営業時間を延長するケースも。
- 空港内の100均は、早朝や深夜のフライト利用者向けに24時間営業や長時間営業を行う店舗がある。
主要エリアの100均店舗
- 東京・大阪・名古屋などの大都市では深夜営業の店舗が点在し、特に繁華街では営業時間が長い傾向にある。
- 地方都市や郊外では営業時間が短めの傾向があり、通常19:00~20:00で閉店する店舗が多い。
- 一部の地方都市では、24時間営業の店舗も増えつつあるが、まだ限定的。
- 駅ビルやターミナル内の100均は、通勤客の需要が高いため、通常より長い営業時間で運営されている。
- 夜勤労働者が多い地域では、深夜営業の店舗が存在する場合がある。
- 繁華街の店舗は、特に週末や祝日前に営業時間を延長することが多い。
深夜営業の店舗リスト
- 一部のダイソーやキャンドゥが深夜営業対応し、大都市圏の主要エリアに集中。
- 東京では新宿・渋谷・池袋などの繁華街に深夜営業店舗が存在。
- 大阪では梅田や難波エリアに夜遅くまで営業する店舗が多い。
- 名古屋では栄エリアを中心に、24時間営業または深夜1:00~2:00まで営業する店舗が増加傾向。
- 札幌、福岡、仙台などの地方都市でも、一部深夜営業の100均が存在するが、数は限られる。
- 観光地や空港周辺では、夜間の利用客を考慮し、深夜まで営業する店舗が増えている。
- 近年、無人レジやAI監視システムを活用し、営業時間の延長を試みる100均も登場している。
なぜ24時間営業の100均が少ないのか
人件費や運営コストの問題
- 深夜営業には追加の人件費が必要であり、昼間に比べてスタッフの確保が難しい。
- 電気代やセキュリティコストも増加し、運営コストが高騰する。
- 深夜帯の店舗管理において、万引き対策やセキュリティ強化が必須となる。
- 24時間営業には品出しや在庫管理を常時行う必要があり、追加コストが発生。
- 一部の店舗では、無人レジやAIを活用した無人店舗の導入により、コスト削減を試みている。
需要と供給のバランス
- 日中と比較して深夜の来店客が少なく、売上が見込めないため、24時間営業を行うメリットが少ない。
- 深夜に利用する顧客層が限られており、通常の日中営業と比べて商品の回転率が低い。
- 需要があるエリアでは深夜営業を実施する店舗もあるが、全体的には少数派。
- 特定のエリアでは、コンビニやドン・キホーテなどが代替店として機能し、100均の24時間営業の需要が薄れることも。
- 深夜営業の店舗が増えると、昼間の売上が分散し、全体的な収益低下につながる可能性がある。
地域ごとの営業方針の違い
- 繁華街や駅前は深夜営業向きであり、24時間営業の可能性が比較的高い。
- 住宅街や郊外では深夜営業の需要が低く、通常の営業時間で運営する店舗が大半。
- 一部の地方都市では、観光地に近い100均が深夜営業を実施するケースもある。
- 夜間の交通量が多いエリアでは、深夜営業の店舗が一定の需要を持つが、全国的にはまだ少数。
- 深夜営業を実施する店舗では、特定の商品に特化し、日中とは異なる商品ラインナップを展開するケースもある。
- 地域によって防犯対策の規制が異なり、一部のエリアでは深夜営業が制限されることも。
100均の24時間営業は、運営コストや需要のバランスの問題から、まだ限定的です。しかし、AI技術や無人レジの導入が進めば、今後は営業時間の柔軟性が高まり、より多くの店舗で深夜営業が実現する可能性があります。
100均の深夜営業店舗
大阪にある24時間営業の店舗
- 一部のダイソーやローカル100均で実施。
- 繁華街(ミナミ・梅田)に集中。
- 大阪駅周辺では、夜勤労働者や観光客向けの店舗も深夜営業を展開。
- 夜遅くまで営業している100均の多くは商業施設やコンビニ併設型が中心。
- 一部の24時間営業店舗では、季節限定商品や食品類の品揃えが充実している。
東京の100均深夜営業事情
- 新宿・渋谷・池袋などの繁華街で限定的に営業。
- 主要駅周辺でコンビニ併設型が多い。
- 東京の24時間営業100均は、特に観光客の利用が多い。
- 繁華街の店舗では、外国人観光客向けの商品が充実している。
- 一部の駅ナカ店舗では、24時間営業を検討する動きも見られる。
札幌・名古屋の営業状況
- 札幌では駅周辺の一部100均が深夜営業対応。
- 名古屋は繁華街や大須エリアに限定。
- 札幌では冬季に防寒用品の深夜販売が増える傾向。
- 名古屋の夜間営業100均は、飲食街周辺での営業が活発。
- 地域特化型の品揃えを強化し、夜間利用者の利便性を高めている。
100均の利用スタイル
深夜の買い物事情
- 仕事終わりや急な買い物で利用。
- 旅行者やイベント帰りの人も多い。
- 深夜は食品や日用品の購入率が高く、特に急なニーズに応える商品が売れやすい。
- 週末や祝日前は、繁華街の100均で夜間利用者が増加。
- 長時間営業の店舗では、深夜限定の割引セールを実施することも。
クレジットカードや電子マネーの利用
- キャッシュレス決済対応の店舗が増加。
- 深夜営業店舗ではセルフレジ導入も。
- QRコード決済や交通系ICカードが利用できる店舗が多い。
- 深夜帯の利用者は、現金よりもキャッシュレス決済を好む傾向がある。
- 無人レジやスマホ決済を活用し、効率的な運営が進められている。
家族向けと個人向けの利用シーン
- 家族連れは日中利用が中心。
- 個人の急な買い物は深夜利用が多い。
- 深夜は単身者や夜勤労働者の利用が中心で、日用品や食品の購入が目立つ。
- 学生や若年層は、イベント帰りや夜遊び後に立ち寄ることが多い。
- 100均の利便性が高まり、夜間需要に合わせた商品展開も進んでいる。
100均専門店とディスカウントストア
DAISOとキャンドゥの特徴
- DAISO:全国展開し、豊富な品揃えで知られる。生活雑貨、文房具、食品、DIY用品など幅広いカテゴリーの商品を取り扱い、100円以外の価格帯の商品も増加傾向にある。さらに、オンラインショップの展開により、店舗に足を運ばなくても購入が可能になっている。
- キャンドゥ:都市部に多く展開し、デザイン性の高い商品やトレンドを意識したラインナップが特徴。キャンドゥ独自のPB(プライベートブランド)商品が増えており、ファッション雑貨やコスメなど若年層向けの商品展開が進んでいる。また、スーパーマーケットやドラッグストア内に出店するケースも増えており、利便性の高い立地が魅力。
- セリア:おしゃれなデザインのアイテムが多く、インテリア雑貨やキッチン用品に強みを持つ。ナチュラルなデザインが人気で、DIYやハンドメイド愛好者にも支持されている。
24時間営業の利便性
- 深夜の突発的なニーズに対応可能。例えば、急に必要になった文房具や工具、消耗品などを購入できる。
- 夜間勤務やシフトワークをする人々にとって便利で、仕事帰りや早朝の買い物が可能になる。
- 旅行者や夜型生活の人にも利便性が高く、特に繁華街や観光地においては利用者が多い。
- しかし、コスト面の課題が大きく、人件費・光熱費の負担が増加するため、多くの店舗で24時間営業の実施が難しい。
- セルフレジや無人レジを活用することで、深夜営業のハードルを下げる取り組みも進行中。
他の深夜営業店舗との比較
- コンビニ:24時間営業が基本だが、100均と比べて品揃えが限られる。特に文房具やキッチン用品、収納グッズなどの種類が少なく、100均でしか手に入らない商品も多い。
- ドン・キホーテ:24時間営業の店舗が多く、100均の商品に近いものも深夜購入可能。価格帯はやや高めだが、幅広いカテゴリーの商品が揃い、食品や家電なども同時に購入できるメリットがある。
- スーパーマーケット:一部のスーパーでは24時間営業を行っており、100均の商品と似た日用品や食品を扱っているが、品揃えが店舗によって異なる。
- ホームセンター:工具やDIY用品が豊富だが、24時間営業の店舗は少なく、営業時間が限られている。
- ネット通販:Amazonや楽天などで24時間購入できるが、即時入手できないため、急ぎの際は実店舗が便利。
24時間営業のお店の探し方
近くの100均の検索方法
- Googleマップで「100均 24時間」と検索し、現在地周辺の深夜営業店舗を確認。
- 店舗の公式サイトやSNSで最新の営業時間情報を確認。
- 口コミサイトやレビューアプリで利用者の投稿をチェックし、深夜営業の有無や店舗の特徴を把握。
- ナビアプリを利用し、最寄りの100均までのルートを確認。
営業時間を調べる便利なツール
- 100均チェーンの公式アプリやナビサイトで営業時間を確認。
- 口コミサイトやSNSを活用し、リアルタイムの情報を収集。
- 店舗に直接電話をして営業時間の詳細を問い合わせる。
- Googleマップの営業時間情報をチェックし、最新の更新情報を確認。
- TwitterやInstagramのハッシュタグ検索を利用し、利用者の投稿から営業時間の実態を調べる。
- 商業施設の公式サイトで、テナント店舗の営業時間一覧を確認。
口コミや評判のチェック
- 実際に利用した人の声を参考にし、営業時間だけでなく、品揃えや店舗の清潔さも確認。
- 店舗によって品揃えが異なるため、目的の商品があるかどうか事前にチェック。
- SNSで「#100均24時間」などのハッシュタグを検索し、リアルな利用者の声を確認。
- YouTubeで店舗紹介動画をチェックし、実際の雰囲気や利便性を確認。
- 利用者のレビューを比較し、価格や利便性に関する評価を考慮して選択。
- 近隣店舗との比較を行い、より利便性の高い店舗を見つける。
24時間営業の100均は少ないものの、需要は確実に存在しており、今後の店舗戦略や技術の発展により、より多くの深夜営業店舗が誕生する可能性がある。特に無人店舗やセルフレジの導入が進めば、コストの問題を克服しやすくなり、100均業界の営業時間の概念が変わるかもしれない。
100均の地域別事情
福岡・熊本エリアの深夜営業
- 福岡市内は一部店舗で深夜営業あり。
- 熊本は深夜営業店舗が少なめ。
- 福岡では天神・博多エリアを中心に、深夜営業を行う店舗が増加傾向。
- 観光地や歓楽街が近いエリアでは、夜間の需要が高まりつつある。
- 熊本では大型商業施設内の100均が夜遅くまで営業しているケースがある。
- 一部の100均では24時間営業のスーパーと提携し、夜間利用者に対応。
埼玉・千葉の店舗事情
- 埼玉は大宮・川越周辺で深夜営業店舗あり。
- 千葉は駅周辺や繁華街に限定。
- 埼玉の越谷や所沢など、大型ショッピングモール内にある100均の営業時間が延長される傾向。
- 千葉では幕張や成田空港周辺で観光客向けの深夜営業100均が増えている。
- 埼玉・千葉の一部100均は、24時間営業のドン・キホーテと併設し、深夜利用が可能な店舗も。
地域ごとの顧客ニーズの違い
- 都市部:深夜営業の需要が高い。
- 郊外・地方:日中利用が中心。
- 都市部では仕事帰りのビジネスパーソンや夜勤労働者の利用が多い。
- 学生街では、深夜まで開いている100均が勉強や部活動帰りの学生に人気。
- 郊外では家族連れが日中の時間帯に集中し、深夜の利用者が少ないため、営業時間を短縮する店舗が多い。
- 地域ごとのライフスタイルに合わせた柔軟な営業時間の設定が求められるようになっている。
100均の未来
24時間営業の可能性
- 人件費削減のため、セルフレジの導入が進めば可能性あり。
- しかし、コスト面の課題が依然として大きい。
- セキュリティの向上とAI技術の発展により、無人店舗の運営が可能になるかもしれない。
- シェアリングエコノミーの概念を活用し、夜間帯のみ営業するモデルの導入が考えられる。
- デジタル技術の進化で、遠隔監視と管理ができるため、安全な夜間営業の実現が可能になる。
新しい営業形態の提案
- 一部時間帯のみセルフサービス化。
- コンビニ併設型の店舗増加。
- 自動販売機形式の100均コーナーの導入。
- 一部商品に特化した24時間営業のミニ店舗の設置。
- アプリやQRコード決済を活用した完全無人レジシステムの拡大。
- ネット注文と店舗受け取りを融合したハイブリッド型の営業方式。
今後の業界トレンド
- ECサイトと実店舗の融合。
- 無人店舗・キャッシュレス決済の普及。
- 需要に応じた営業時間の多様化。
- AIを活用した需要予測により、営業時間をフレキシブルに調整。
- 店舗の多目的利用(カフェ併設やワークスペースとしての活用)。
- サブスクリプションモデルを導入し、一定額で一定の商品が利用できる仕組みの検討。
- ドライブスルー型の100均店舗の設置による利便性向上。
まとめ
100均の24時間営業は、深夜の突発的な買い物ニーズに応える便利な選択肢ですが、人件費や運営コスト、需要のバランスなどの課題から、日本ではまだ一般的ではありません。特に、深夜の来店客数が限られていることや、スタッフの確保が難しい点が大きな障壁となっています。
しかし、都市部の繁華街や駅周辺では、夜間営業を行う100均が少しずつ増えており、今後もテクノロジーの進化によって深夜営業が拡大する可能性があります。無人レジやAI監視システムの導入により、人件費の削減が進めば、これまで難しかった24時間営業も現実的になるかもしれません。
また、コンビニやドン・キホーテといった24時間営業の競合とどのように差別化していくかも重要なポイントです。例えば、一部時間帯のみセルフサービス化する、特定の商品に特化したミニ店舗を設置するなど、新たなビジネスモデルの導入が求められるでしょう。
100均業界は、今後も消費者のライフスタイルに合わせた柔軟な営業形態を模索し続けるはずです。深夜に100均での買い物が当たり前になる日は、そう遠くないのかもしれません。
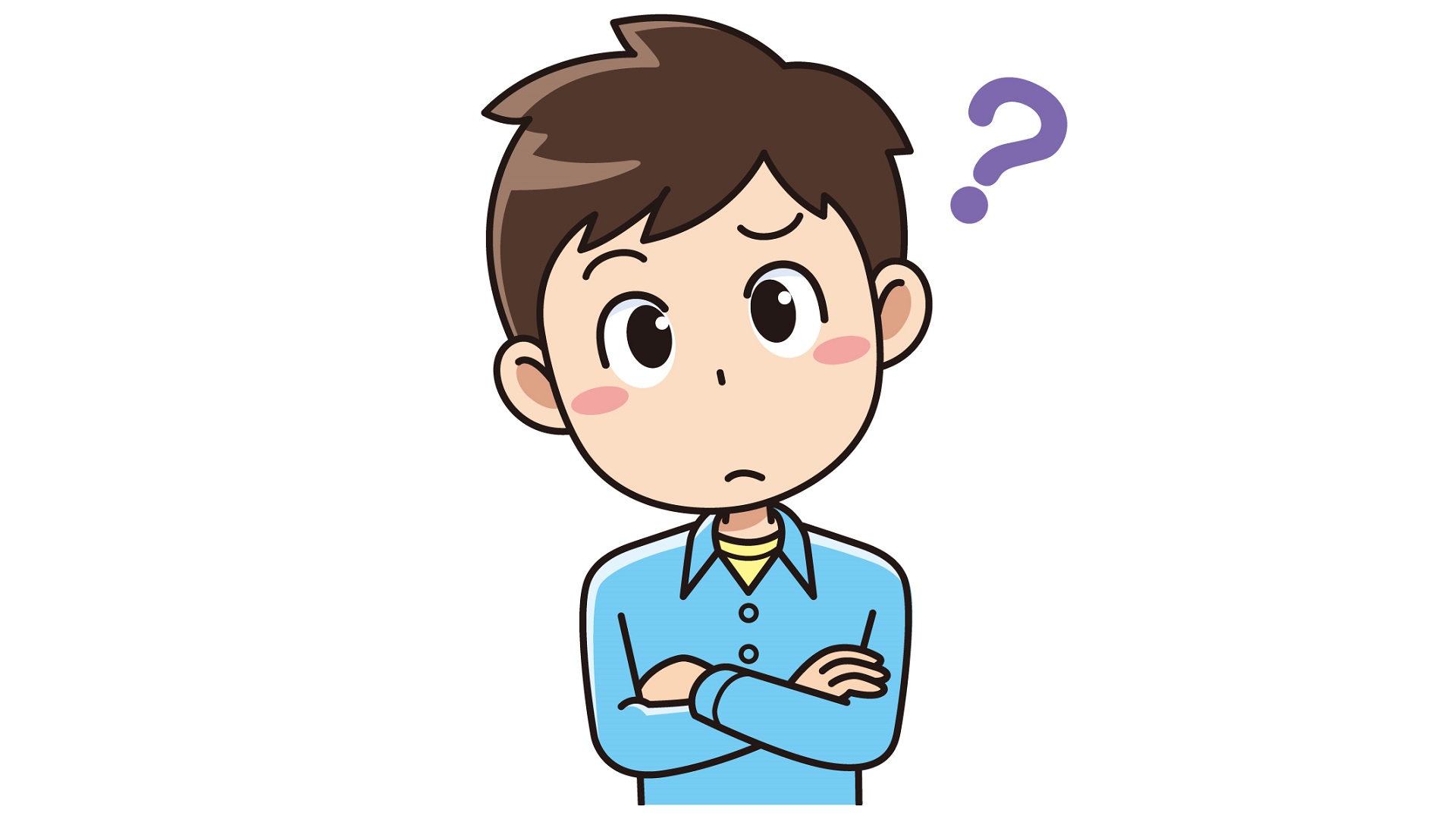

コメント