スマートフォンや携帯電話に「通知不可能」や「非通知」と表示された着信が入ると、驚きや不安を感じる人は多いものです。
特に相手が「警察です」と名乗った場合、本当に警察なのか疑問を抱きながらも、応答すべきか迷ってしまう場面は少なくありません。
近年、特殊詐欺グループが警察や役所、金融機関を装って電話をかけ、個人情報や金銭をだまし取る手口が急増しています。こうした電話は一見すると本物らしく聞こえますが、冷静に確認しなければ被害につながる危険性が高いのです。
この記事では、通知不可能・非通知の着信にどう対応すべきか、またうっかり応答してしまった場合に取るべき行動を、実例を交えて詳しく解説します。
警察が非通知で電話をかけるケースはあるのか?
まず理解しておきたいのは、本物の警察が一般市民に非通知で連絡するのは非常にまれだという点です。
通常、警察からの公式な連絡は、警察署や交番の固定電話番号が表示されます。これは記録の正確性や信頼性を確保するための基本的な運用です。
しかし、例外的に非通知で発信する場合も存在します。
-
捜査上の機密保持が必要な場合
重大事件の関係者に聞き取りを行う際や、情報提供者の身の安全を守るため、あえて番号を非表示にして発信することがあります。
この場合、相手の安全や事件解決のため、非通知が意図的に利用されます。 -
現場からの緊急連絡
事故や事件の第一報として、現場の警察官が個人携帯から発信する際、非通知設定になってしまうことがあります。これは現場の状況や使用端末によるもので、恒常的な運用ではありません。
ただし現実には、「警察です」と名乗る非通知着信の大半は詐欺である可能性が高く、特に高齢者を狙った架空請求や還付金詐欺でよく使われています。
本物か偽物かを判断する確認手順
怪しいと感じたら、感情的に動くのではなく、以下の流れで確認してください。
-
所属部署と担当者名を聞く
例:「○○警察署刑事課の△△です」と名乗らせる。 -
「こちらからかけ直します」と伝える
その際、必ず電話番号は相手から聞かず、自分で調べること。 -
最寄りの警察署の代表番号に連絡
公式サイトや電話帳で確認した番号を使用する。 -
担当者が実在するか照会
名前と用件を伝え、事実確認を行う。
正規の警察官であれば、こうした確認を拒むことはありません。むしろ、冷静な対応を歓迎してくれるでしょう。
応答してしまった場合の料金や危険性
非通知電話に出ても、基本的には通話料は発生しません。しかし、次のような手口には要注意です。
-
国際ワン切り詐欺
海外番号から1〜2コールだけ鳴らし、折り返し電話を誘導します。かけ直すと国際通話料金が1分数百円〜数千円発生することがあります。 -
自動音声ガイダンスによる操作
「○番を押してください」と案内され、押すと有料回線や詐欺サービスに接続される場合があります。 -
個人情報の聞き出し
住所、氏名、生年月日、家族構成、銀行口座などは絶対に伝えないこと。これらは後日別の詐欺で利用される可能性があります。
実際に、知人が非通知電話に応答して個人情報を伝えてしまい、その後しばらく不審な郵便物や電話が続いた事例もあります。
事前にできるブロック設定と予防策
詐欺電話から身を守るためには、日頃からスマホや携帯電話の設定を見直しておくことが有効です。
-
iPhoneの場合
「設定」→「電話」→「不明な発信者を消音」をオンにすると、登録外の番号は自動的に留守番電話に転送されます。 -
Androidの場合
「電話」アプリの設定にある「着信拒否」「迷惑電話ブロック」機能で、非通知をまとめて拒否できます。 -
通信キャリアのサービス
- ドコモ:迷惑電話ストップサービス(無料)
- au:迷惑電話撃退サービス(月額110円)
- ソフトバンク:ナンバーブロック(月額110円) -
アプリでの防御
「Truecaller」や「Whoscall」などは、着信時に相手番号の危険性を表示し、ユーザーの共有データを活用して詐欺の可能性を警告します。
被害・不安を感じたらすぐ相談
-
警察相談専用電話(#9110)
24時間対応。緊急性がない詐欺相談に適しています。 -
消費者ホットライン(188)
詐欺や悪質商法など幅広く対応。 -
金融機関
口座情報を伝えてしまった場合は、すぐに利用停止や監視を依頼しましょう。
相談時には、通話時間、相手の名乗り、発言内容をできるだけ詳細に記録しておくと対応がスムーズです。
まとめ
非通知や通知不可能の電話は、まず疑ってかかることが大切です。
本当に必要な連絡なら、正規の番号から再度かかってきます。
着信拒否設定や迷惑電話対策サービスを活用し、「知らない番号には出ない」という習慣を持つことが、被害を防ぐ第一歩です。
少しでも違和感を覚えたら、その直感を信じ、冷静かつ慎重に行動しましょう。
日常的に対策を講じることで、安全な通信環境を維持できます。

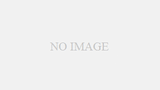
コメント